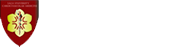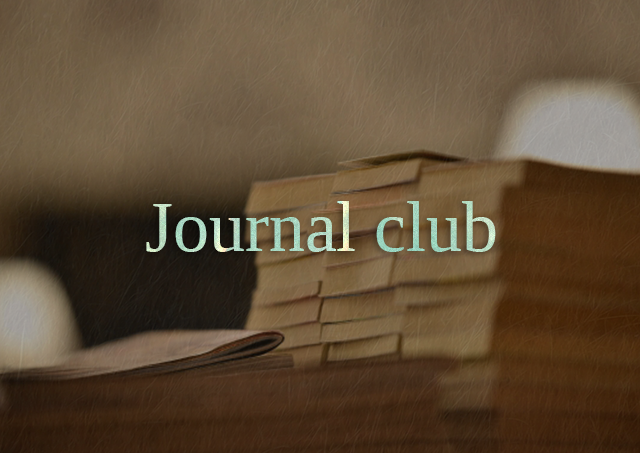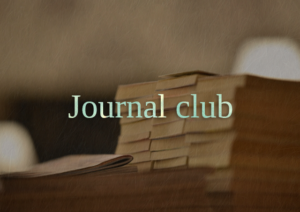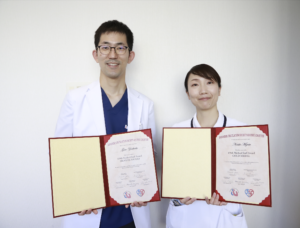Beta-Blockers after Myocardial Infarction and Preserved Ejection Fraction
N Engl J Med.2024 Apr 18;390(15):1372-1381.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2401479
心筋梗塞後のβ遮断薬治療の有用性を示した試験のほとんどは、心筋梗塞患者を対象としたものであり、近代的なバイオマーカーに基づく心筋梗塞診断やPCI,抗血栓薬やスタチンなどの集学的治療が行われる以前のものである。本試験は、現代の心筋梗塞診療において、EFが保たれた心筋梗塞へのβブロッカーの有用性を検討されています。
本試験は、スウェーデンを中心とする45施設で行われた非盲検試験において、冠動脈造影を受けた左室駆出率が50%以上の急性心筋梗塞患者を,β遮断薬(メトプロロールまたはビソプロロール)群と非β遮断薬群に無作為に割り付けています。主要エンドポイントは死亡・心筋梗塞の複合です。
結果ですが、2017年9月から2023年5月までに、合計5020例の患者が登録されました(95.4%がスウェーデンの患者)。追跡期間中央値は3.5年(四分位範囲2.2~4.7)。心不全歴もかなり少ない群の、心筋梗塞症例が対象となっています。主要エンドポイントはβ遮断薬群では2508例中199例(7.9%)に、β遮断薬非投与群では2512例中208例(8.3%)に発生した(ハザード比、0.96;95%信頼区間、0.79〜1.16;P = 0.64)。β遮断薬投与は副次的エンドポイントの累積発生率の低下との相関はありませんでした。
Safety エンドポイントに関しては、徐脈、第2度または第3度房室ブロック、低血圧、失神、ペースメーカー植え込みによる入院はβ遮断薬群で3.4%、β遮断薬非投与群で3.2%、喘息または慢性閉塞性肺疾患による入院はそれぞれ0.6%と0.6%、脳卒中による入院は1.4%と1.8%でした。
研究の限界として、非盲検試験である点、クロスオーバーが発生している点(非βブロッカー群では1年後に14%がβ内服している)等があげられています。
本論文では、PCIを受けた急性心筋梗塞患者で左室駆出率が保たれていた(50%以上)場合、β遮断薬の長期投与は複合心筋梗塞のリスクを低下させることはなかった、と結論づけています。
発表後は以下の内容で議論が行われました。
・現代の治療が行われており、イベント率自体が少なかった。
・βブロッカーの種類による影響はあるのか
・βブロッカー内服量を勘案しているのか
・サブ解析に結果について
発表:中島 文責:吉岡